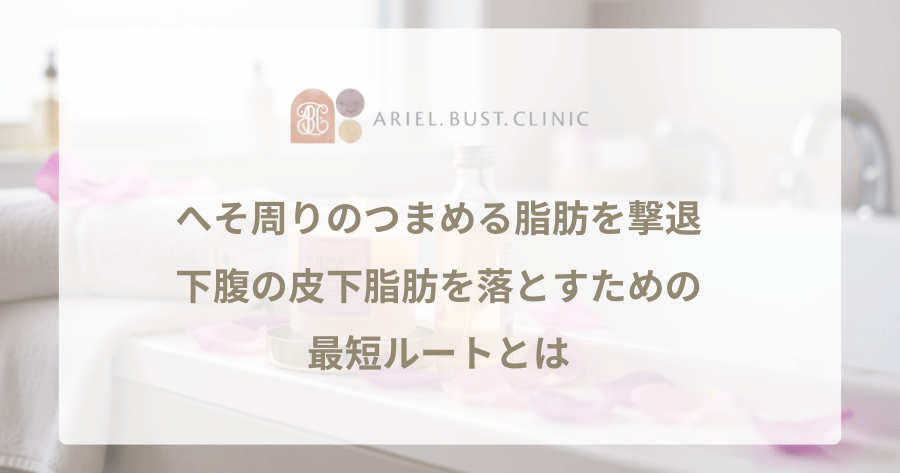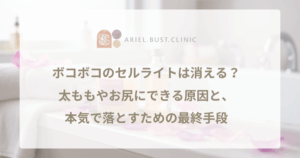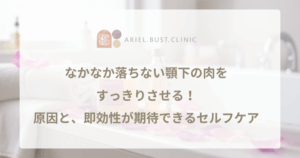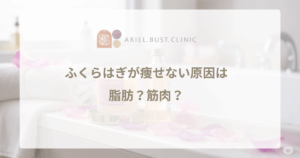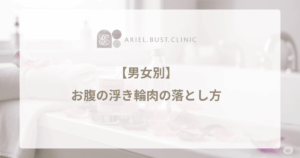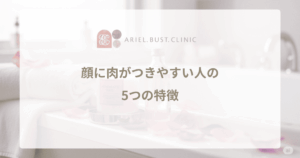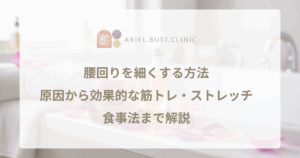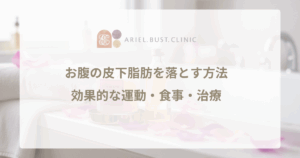ふとした時に気になる、へその下のぽっこりとした膨らみ。指でつまめてしまうその脂肪に、ため息をついている方も多いのではないでしょうか。
この「つまめる脂肪」の正体は、主に皮下脂肪です。下腹部、特にへそ周りは皮下脂肪が蓄積しやすく、一度つくと自力で落とすのが非常に難しい部位です。
この記事では、へそ周りに脂肪がつく原因から、セルフケアでの落とし方、そして多くの方が直面する限界、さらにはその脂肪を撃退するための「最短ルート」について、詳しく解説していきます。
資格・所属
- 日本形成外科学会専門医
- コンデンスリッチファット(CRF)療法認定医
- VASER Lipo認定医
- Juvederm Vista 認定医
- 乳房再建用エキスパンダー/インプラント実施医師
- 日本形成外科学会所属
- 日本美容外科学会(JSAPS)所属
【略歴】
脂肪吸引、豊胸を専門としている形成外科専門医。獨協医科大学医学部卒業後、獨協医科大学病院形成外科・美容外科入局。足利赤十字病院形成外科、獨協医科大学埼玉医療センター 形成外科学内助教、THE CLINIC大阪院・名古屋院の副院長を経て2024年、名古屋にARIEL .BUST.CLINICを開院。
ARIEL .BUST.CLINICは、脂肪吸引を得意とする名古屋のクリニックです。それぞれの体型や悩みに応じた専門性を活かしたご提案をしており、傷跡や傷のケアに形成外科専門医としての知識と技術を評価いただき、全国から患者様にお越しいただいています。
ボディメイクは決して焦る必要のないものです。このサイトでは脂肪吸引に関連する多くの記事を書いていますので、すぐに施術を決めることはせず、まずはぜひ患者様自身で知識をつけた上でご希望のクリニックへ相談されるようにしてください。
なぜ?へそ周り・下腹につまめる脂肪がつく原因
へそ周りや下腹部の脂肪が気になる方は多くいます。この部位は、体の構造上、脂肪が蓄積しやすい場所の一つです。
特に「つまめる脂肪」として認識されるのは、皮膚のすぐ下にある「皮下脂肪」です。なぜこの部分に脂肪が集中してしまうのか、その原因を探ります。
皮下脂肪と内臓脂肪の違い
体につく脂肪には、大きく分けて「皮下脂肪」と「内臓脂肪」の二種類があります。へそ周りで指でつまめる脂肪は、皮下脂肪です。この二つの脂肪は、つく場所も性質も異なります。
皮下脂肪の特徴
皮下脂肪は、その名の通り皮膚のすぐ下に蓄積する脂肪です。全身につきますが、特に下腹部、お尻、太ももといった部位に多くつきます。
女性は男性に比べて皮下脂肪がつきやすい傾向があります。皮下脂肪は、体温維持や外からの衝撃を和らげるクッションの役割を果たします。
エネルギーの貯蔵庫でもあり、ゆっくりと蓄積され、消費されるのもゆっくりという特徴があります。これが、へそ周りの脂肪が一度つくと落ちにくい大きな理由です。
内臓脂肪の特徴
内臓脂肪は、胃や腸などの内臓の周りに蓄積する脂肪です。外見からは分かりにくいですが、お腹がぽっこりと出ている場合、内臓脂肪が多い可能性があります。
こちらは男性につきやすい傾向があります。内臓脂肪は皮下脂肪と比べて蓄積しやすく、また消費されやすいという特徴を持ちます。
しかし、内臓脂肪が過剰に蓄積すると、生活習慣病のリスクを高めることが知られています。
へそ周りに脂肪がつきやすい生活習慣
日々の生活習慣が、へそ周りの皮下脂肪蓄積に大きく影響します。特に現代人に見られがちな習慣が、脂肪をため込む原因となっています。
食生活の偏りと脂肪蓄積
消費カロリーよりも摂取カロリーが多い状態が続くと、余ったエネルギーが脂肪として蓄えられます。
特に、脂質の多い揚げ物や、糖質の多いお菓子、ジュース、炭水化物の過剰摂取は、中性脂肪を増やし、皮下脂肪の蓄積に直結します。
また、早食いや不規則な食事時間も、血糖値の急激な上昇を招き、脂肪をため込みやすくします。
運動不足による基礎代謝の低下
日常生活での活動量が少なかったり、運動習慣がなかったりすると、消費カロリーが減るだけでなく、筋肉量も低下します。
筋肉は、私たちが安静にしている時でもエネルギーを消費する「基礎代謝」の大部分を担っています。
筋肉量が減ると基礎代謝が低下し、同じ量を食べても太りやすく、脂肪が燃焼しにくい体質になってしまいます。
姿勢の悪さ
デスクワークやスマートフォンの長時間使用による猫背などの悪い姿勢は、腹部の筋肉(腹筋群)が使われにくい状態を作ります。
筋肉が緩むと、その部分に脂肪がつきやすくなるだけでなく、内臓が下垂して下腹部がぽっこりと出やすくなる原因にもなります。
加齢による基礎代謝の変化
年齢を重ねることも、へそ周りの脂肪がつきやすくなる要因の一つです。これは、加齢に伴う体の自然な変化が関係しています。
ホルモンバランスの影響
加齢、特に30代後半から40代以降になると、基礎代謝は徐々に低下していきます。これは筋肉量の自然な減少が主な原因です。また、ホルモンバランスの変化も影響します。
特に女性の場合、女性ホルモン(エストロゲン)には内臓脂肪の蓄積を抑え、皮下脂肪を適度に保つ働きがありますが、更年期に近づきエストロゲンの分泌が減少すると、内臓脂肪がつきやすくなると同時に、皮下脂肪の代謝も落ちやすくなります。
へそ周りの脂肪が落ちにくい理由
「ダイエットを頑張っているのに、へそ周りだけが痩せない」という悩みは非常によく聞かれます。これには、生物学的な理由と皮下脂肪特有の性質が関係しています。
下腹部は脂肪が蓄積されやすい部位
人間の体は、生命維持のためにエネルギーを蓄えようとします。
下腹部や腰回り、お尻などは、内臓を守ったり、妊娠・出産に備えたりする観点から、優先的に脂肪(特に皮下脂肪)を蓄積するようになっています。
これは、飢餓状態から身を守るための本能的な仕組みとも言えます。
皮下脂肪の性質と燃焼の順番
体がエネルギーを必要とするとき、脂肪は分解されて使われますが、燃焼しやすい脂肪とそうでない脂肪があります。
一般的に、内臓脂肪の方が皮下脂肪よりも先に燃焼されやすい傾向があります。
脂肪燃焼の一般的な順番
ダイエットを開始すると、まず内臓脂肪が減り始め、その次に皮下脂肪が減っていきます。さらに皮下脂肪の中でも、燃焼される順番があると言われています。
一般的には、肝臓から遠い部位、例えば手首や足首から細くなり始め、お腹周りや太もも、お尻といった脂肪の多い部分は、最後まで残りがちです。
へそ周りの皮下脂肪は、この「最後に落ちる脂肪」の代表格なのです。
間違ったダイエット方法の影響
早く痩せたい一心で、極端な食事制限を行うことも、へそ周りの脂肪が落ちにくくなる原因となります。
食事制限だけでは筋肉も落ちる
食べる量を極端に減らすと、体はエネルギー不足を補うために、脂肪だけでなく筋肉も分解してエネルギー源として使おうとします。筋肉量が減ってしまうと、前述の通り基礎代謝が低下します。
その結果、消費カロリーが減り、さらに痩せにくい体質になるという悪循環に陥ります。そして、ダイエットをやめた途端にリバウンドしやすく、その際につくのは筋肉ではなく脂肪です。
自分でできる!へそ周りの脂肪を落とす試み
へそ周りの皮下脂肪は落ちにくいですが、自力での努力が全く無駄というわけではありません。
地道な継続が必要ですが、生活習慣の改善によって、体全体の脂肪を減らし、結果としてへそ周りの脂肪を減らしていくことは可能です。
食生活の見直しと改善
皮下脂肪を落とす基本は、摂取カロリーと消費カロリーのバランスを改善することです。
摂取カロリーが消費カロリーを上回らないようにコントロールしつつ、必要な栄養素はしっかり摂ることが重要です。
糖質・脂質のコントロール
脂肪の元となる糖質や脂質の過剰摂取を控えることが第一歩です。甘いお菓子やジュース、スナック菓子、脂身の多い肉、揚げ物などは量を減らしましょう。
ただし、糖質も脂質も体に必要なエネルギー源であるため、完全にカットするのではなく、「摂りすぎない」意識が大切です。
タンパク質と食物繊維の積極的な摂取
筋肉の材料となるタンパク質は、意識して摂取する必要があります。鶏むね肉、ささみ、魚、大豆製品、卵など、良質なタンパク質源を選びましょう。
また、食物繊維は血糖値の急激な上昇を抑えたり、腸内環境を整えたりする働きがあります。野菜、きのこ類、海藻類を毎食取り入れるよう心がけてください。
食事改善のポイント
日々の食事で意識したいポイントをまとめます。
| 項目 | 意識するポイント | 具体例 |
|---|---|---|
| カロリー | 摂取<消費 | 揚げ物を蒸し物や焼き物に変える、間食を控える |
| 栄養バランス | PFCバランス(タンパク質・脂質・炭水化物) | 高タンパク・低脂質・中糖質を意識、野菜を先に食べる |
| 食物繊維 | 腸内環境の整備 | 毎食、野菜や海藻類を一品加える、玄米や雑穀米を選ぶ |
有酸素運動で脂肪を燃焼
脂肪をエネルギーとして直接消費するためには、有酸素運動が効果的です。ウォーキング、ジョギング、サイクリング、水泳など、自分が継続しやすいものを選びましょう。
有酸素運動の目安
一般的に、脂肪燃焼が本格的に始まるのは運動開始から20分程度経過してからと言われていますが、短い時間でもこまめに行うことで効果は期待できます。
まずは「1日合計30分」を目指すなど、無理のない範囲で生活に取り入れることが継続のコツです。
有酸素運動の種類と特徴
代表的な有酸素運動の特徴を紹介します。
| 運動の種類 | 特徴 | 推奨時間(目安) |
|---|---|---|
| ウォーキング | 最も手軽で、関節への負担が少ない | 30分〜1時間/日 |
| ジョギング | ウォーキングより消費カロリーが多い | 20分〜30分/日 |
| 水泳 | 全身運動で消費カロリー大、浮力で関節への負担小 | 30分以上/週2〜3回 |
筋力トレーニングで基礎代謝アップ
有酸素運動と並行して行いたいのが筋力トレーニングです。筋肉量を増やすことで基礎代謝が上がり、日常生活での消費カロリーが増え、痩せやすく太りにくい体質を目指せます。
下腹部に効く筋トレ例
へそ周りが気になるからといって、腹筋運動(クランチ)ばかりを行うのは効率的ではありません。
もちろん腹筋を鍛えることも大切ですが、まずは全身の大きな筋肉(太もも、背中、胸など)を鍛えるスクワットや腕立て伏せ、懸垂(またはそれに類するマシン)などが、基礎代謝アップには効果的です。
その上で、下腹部を意識したレッグレイズ(仰向けで脚を上げ下げする)やプランク(体幹トレーニング)を取り入れると良いでしょう。
筋トレと基礎代謝の関係
筋肉は体の中で最も多くのエネルギーを消費する組織の一つです。筋トレによって筋肉量が増加すると、運動していない時でも消費されるカロリー量(基礎代謝)が増加します。
これにより、同じ食事量でも脂肪がつきにくくなります。
セルフケアの限界と現実
ここまで紹介した食生活の改善や運動は、健康維持や体全体の脂肪を減らす上で非常に重要です。
しかし、こと「へそ周りのつまめる皮下脂肪」だけを狙って落とすことに関しては、セルフケアには限界があります。
皮下脂肪は自力で落とすのが難しい
繰り返しになりますが、皮下脂肪は非常に落ちにくい性質を持っています。特に、へそ周りのような局所的な皮下脂肪は、体全体の脂肪がある程度落ちた後でなければ、なかなか変化を実感できません。
ダイエットをしても、顔や胸から痩せてしまい、肝心の下腹部は最後まで残ってしまう、という経験を持つ方も少なくないでしょう。
ダイエット成功までに時間がかかる
セルフケアでへそ周りの脂肪に目に見える変化をもたらすには、数ヶ月から年単位での地道な継続が必要です。
その間、厳しい食事管理と運動習慣を維持し続けなければなりません。
継続の難しさ
多くの場合、効果がなかなか現れないことでモチベーションを維持することが難しくなり、途中で挫折してしまうケースが後を絶ちません。
また、仕事や私生活の忙しさの中で、完璧な食事管理や運動時間を確保し続けること自体が現実的でない場合もあります。
リバウンドの可能性
無理な食事制限やハードすぎる運動で一時的に体重を落とせても、その生活を続けられなくなれば、すぐにリバウンドしてしまいます。
特に筋肉量が落ちて基礎代謝が低下した状態でのリバウンドは、以前よりも脂肪がつきやすい体質になってしまう可能性があります。
セルフケアの注意点
自力でのダイエットには、いくつかの注意点が存在します。
| 注意点 | 理由 | 対策 |
|---|---|---|
| 過度な食事制限 | 基礎代謝の低下、栄養失調、リバウンドのリスク | バランスの取れた食事を基本とし、摂取カロリーを調整する |
| 誤った筋トレフォーム | 怪我の原因となる、狙った筋肉に効かない | 専門家の指導を受ける、動画などで正しいフォームを学ぶ |
| 短期間での成果を求める | 継続が困難になり、挫折しやすい | 長期的な視点を持ち、小さな目標(例:1ヶ月1kg減)を設定する |
へそ周りの脂肪撃退「最短ルート」は脂肪吸引
セルフケアでの部分痩せが非常に困難であるのに対し、医療の力で特定の部位の脂肪を直接取り除く方法があります。それが「脂肪吸引」です。
へそ周りのつまめる皮下脂肪を確実に取り除きたい場合、脂肪吸引は最も効果的で「最短ルート」と言える選択肢の一つです。
脂肪吸引とは?
脂肪吸引は、美容医療の手術の一つです。
皮膚に数ミリ程度の小さな切開を加え、そこから「カニューレ」と呼ばれる細い管を挿入し、皮下脂肪層にある脂肪細胞を直接吸引して体外へ排出する施術です。
脂肪吸引の基本的な仕組み
ダイエット(食事制限や運動)は、一つ一つの脂肪細胞を「小さくする」ことで痩せますが、脂肪細胞の「数」は減りません。
そのため、食事を元に戻せば脂肪細胞は再び大きくなり、リバウンドします。一方、脂肪吸引は、脂肪細胞そのものを物理的に吸引して取り除くため、脂肪細胞の「数」自体を減らすことができます。
なぜ脂肪吸引が「最短ルート」なのか
脂肪吸引が「最短ルート」と呼ばれる理由は、その確実性と即効性(※腫れが引いた後の効果)にあります。
確実な部分痩せ効果
最大の利点は、ダイエットでは不可能な「部分痩せ」が実現できることです。
へそ周り、下腹部、ウエストラインなど、気になる部位の脂肪だけを狙って除去し、理想のボディラインをデザインすることが可能です。
脂肪細胞の数自体を減らす
脂肪細胞の数自体を減らすため、施術した部位は半永久的に脂肪がつきにくくなります。
もちろん、術後に暴飲暴食を続ければ残った脂肪細胞が大きくなったり、施術していない他の部位が太ったりすることはありますが、施術部位が元の状態に戻るようなリバウンドは極めて起こりにくいです。
脂肪吸引のメリット
へそ周りの脂肪に対して脂肪吸引を選ぶことには、セルフケアにはない多くの利点があります。
脂肪吸引の主な利点
脂肪吸引が選ばれる理由をまとめます。
| メリット | 詳細 |
|---|---|
| 確実な部分痩せ | へそ周りなど、狙った部位の皮下脂肪を直接除去できる |
| リバウンドしにくい | 脂肪細胞の数自体を根本的に減らすため、元に戻りにくい |
| 短期間での効果実感 | セルフケアで何年もかかる変化を、術後のダウンタイム(数ヶ月)を経て実感できる |
脂肪吸引の種類と特徴
一口に脂肪吸引といっても、現代では様々な技術や機器が登場しています。それぞれに特徴があり、患者様の脂肪の質や量、希望する仕上がりに合わせて選択します。
主な脂肪吸引の方法
クリニックでよく用いられる代表的な脂肪吸引の方法を紹介します。これらは、脂肪を吸引しやすくするために、どのように脂肪にアプローチするかが異なります。
- ベイザー脂肪吸引
- アキーセル脂肪吸引
- 従来の脂肪吸引(シリンジ法など)
各種脂肪吸引技術の比較
それぞれの技術には、体への負担やダウンタイム(回復期間)に違いがあります。
| 施術方法 | 特徴 | ダウンタイム(目安) |
|---|---|---|
| ベイザー脂肪吸引 | 特殊な超音波で脂肪細胞だけを遊離させ、周辺組織のダメージを抑えて吸引 | 比較的短め |
| アキーセル脂肪吸引 | 高周波(RFAL)を用い、脂肪を乳化させると同時に皮膚を引き締める効果が期待できる | 短め |
| 従来法(シリンジ法など) | 医師の手作業や機械の陰圧で脂肪を直接吸引。丁寧な施術が可能だが医師の技術に左右される | やや長め |
へそ周り(下腹部)に適した施術
へそ周りを含む下腹部は、吸引する脂肪量が多いケースや、たるみが出やすいケースなど様々です。どの施術方法が最適かは、その人の脂肪のつき方、皮膚の弾力、希望する仕上がりによって異なります。
例えば、脂肪量が多く皮膚のたるみも懸念される場合は、引き締め効果も期待できる機器(ベイザーやアキーセルなど)が推奨されることがあります。
施術選択のポイント
最終的な施術方法は、医師が診察の上で判断します。カウンセリング時に、それぞれの方法のメリット・デメリットをしっかり説明してもらい、納得のいく方法を選ぶことが重要です。
脂肪吸引のリスクとダウンタイム
脂肪吸引は医療行為であるため、リスクや術後のダウンタイムが伴います。これらを正しく理解しておくことは非常に大切です。
ダウンタイム中の主な症状
術後には、一定期間、以下のような症状が現れます。
- 腫れ
- 内出血
- 痛み(筋肉痛に似た痛み)
- 拘縮(こうしゅく)
拘縮とは、脂肪がなくなったスペースの皮膚が治癒する過程で、一時的に硬くなったり、凸凹したりする現象です。
これは術後1週間頃から始まり、1〜3ヶ月程度でピークを迎え、その後徐々に柔らかく滑らかになっていきます。
ダウンタイム症状の経過
症状が現れる時期やピークには個人差がありますが、一般的な目安を示します。
| 症状 | 出現時期(目安) | ピーク(目安) |
|---|---|---|
| 腫れ・内出血 | 術直後〜 | 術後1〜2週間 |
| 痛み | 術直後〜 | 術後数日〜1週間 |
| 拘縮 | 術後1週間〜 | 術後1〜3ヶ月 |
脂肪吸引を受ける前に知っておきたいこと
「最短ルート」である脂肪吸引ですが、満足のいく結果を得るためには、施術を受ける前の準備と心構えが重要です。
クリニック選びの重要性
脂肪吸引の仕上がりは、担当する医師の技術力、経験、そして美的センスに大きく左右されます。また、安全に施術を行うための設備や体制が整っているかも重要です。
良いクリニック選びの基準
何を基準にクリニックを選べば良いか、いくつかのポイントを紹介します。
| チェック項目 | 確認する理由 |
|---|---|
| 医師の経験・症例数 | 脂肪吸引の技術力と安全管理能力を判断するため |
| カウンセリングの質 | 悩みや希望を正確に理解し、適切な提案とリスク説明をしてくれるか |
| アフターケア体制 | 術後の不安や万が一のトラブル時に、誠実に対応してくれるか |
カウンセリングで確認すべきこと
施術を決める前に、必ず医師によるカウンセリングを受けます。この場で、自分の希望を具体的に伝え、疑問や不安をすべて解消しておく必要があります。
質問リストの準備
緊張して聞き忘れることがないよう、事前に聞きたいことをリストアップしておくと安心です。
- 私のへそ周りの脂肪は皮下脂肪か、内臓脂肪も混じっているか
- 私に最も適した施術法(機器)とその理由は何か
- 具体的なリスク、副作用、合併症の可能性は
- ダウンタイム(腫れ・痛み・拘縮)の詳しい経過と、仕事復帰の目安は
- 必要な費用総額と、その内訳(麻酔代、圧迫着代、術後検診代など)
施術後の注意点とアフターケア
脂肪吸引は、施術が終われば完了ではありません。術後の適切なケアが、美しい仕上がりと早期の回復につながります。
術後の過ごし方
術後は、クリニックの指示に従って過ごすことが大切です。特に重要なのが、施術部位を圧迫する「圧迫固定」です。これは腫れや内出血を抑え、皮膚をしっかりと引き締めるために行います。
一定期間(数日〜1ヶ月程度、クリニックの方針による)、専用のガードルなどを着用します。
また、術後の拘縮を和らげるために、インディバなどの高周波温熱療法や、セルフマッサージを推奨するクリニックもあります。
よくある質問(Q&A)
最後に、へそ周りや下腹の脂肪、脂肪吸引に関して多く寄せられる質問にお答えします。
- へそ周りの脂肪は内臓脂肪ですか?皮下脂肪ですか?
-
指でつまめる脂肪であれば、それは皮下脂肪である可能性が非常に高いです。内臓脂肪は、お腹の中の内臓の周りにつくため、外から指でつまむことはできません。
ただし、皮下脂肪と内臓脂肪の両方が多い場合もあります。正確な診断は、クリニックでのCT検査などで判断できます。
- マッサージやエステでへそ周りの脂肪は落ちますか?
-
マッサージやエステは、血行やリンパの流れを促進し、一時的にむくみを改善させる効果は期待できます。
しかし、これらによって皮下脂肪の細胞そのものを分解したり、数を減らしたりすることは医学的には難しいとされています。
根本的に脂肪を減らすには、継続的なダイエット(食事・運動)か、脂肪吸引などの医療が必要です。
- 脂肪吸引後、すぐにへそ周りがスッキリしますか?
-
いいえ、すぐにはスッキリしません。施術直後は、麻酔液の影響や手術による炎症で、施術前よりも腫れたり浮腫んだりします。
強い腫れや内出血は1〜2週間で徐々に落ち着きますが、その後「拘縮(こうしゅく)」という皮膚が硬くなる時期が始まります。
この拘縮が完全に治まり、皮膚が柔らかく引き締まって最終的な仕上がりとなるまでには、一般的に3ヶ月から半年程度かかります。
- 脂肪吸引をしたら、もう太りませんか?
-
施術した部位は、脂肪細胞の数自体が減っているため、リバウンド(元に戻ること)は極めてしにくいです。しかし、脂肪吸引は「太らない体」にする手術ではありません。
術後も摂取カロリーが消費カロリーを上回る生活を続ければ、残った脂肪細胞が大きくなったり、施術していない他の部位(腕や背中、顔など)に脂肪がついたりすることは十分にあり得ます。
美しい体型を維持するためには、術後もバランスの良い食事や適度な運動を心がけることが大切です。
- 痛みはどのくらい続きますか?
-
痛みの感じ方には個人差がありますが、一般的に術後2〜3日をピークに、1週間程度は強い筋肉痛のような痛みが続きます。
この痛みは、クリニックから処方される鎮痛剤で十分にコントロール可能です。その後は、体を動かした時や触った時の痛みに変わり、1ヶ月程度で徐々に落ち着いていきます。
参考文献
KENNEDY, J., et al. Non‐invasive subcutaneous fat reduction: a review. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, 2015, 29.9: 1679-1688.
WIRTH, Alfred; STEINMETZ, Berit. Gender differences in changes in subcutaneous and intra‐abdominal fat during weight reduction: an ultrasound study. Obesity research, 1998, 6.6: 393-399.
AUH, Sogyong L., et al. Quantification of noninvasive fat reduction: A systematic review. Lasers in Surgery and Medicine, 2018, 50.2: 96-110.
CHASTON, Timothy Bede; DIXON, J. B. Factors associated with percent change in visceral versus subcutaneous abdominal fat during weight loss: findings from a systematic review. International journal of obesity, 2008, 32.4: 619-628.
AL DUJAILI, Zeena, et al. Fat reduction: complications and management. Journal of the American Academy of Dermatology, 2018, 79.2: 197-205.
POLLACK, Sheldon V. Liposuction of the abdomen: the basics. Dermatologic clinics, 1999, 17.4: 823-834.
ARAÚJO, A. R., et al. Effectiveness of Ultra Cavitation in Reducing Abdominal Fat: A Case Study. J Dermat Cosmetol, 2018, 2.1: 76-81.
WU, Zongzhou, et al. A Clinical Early Evaluation of the Combined Use of Low‐Intensity Focused Ultrasound and Radiofrequency for Female Abdominal Contouring. Journal of Cosmetic Dermatology, 2025, 24.7: e70267.
PARAL, J., et al. Comparison of Sutured versus Non-Sutured Subcutaneous Fat Tissue in Abdominal Surgery: A Prospective Randomized Study. European Surgical Research, 2007, 39.6: 350-358.
GRAF, Ruth, et al. Lipoabdominoplasty: liposuction with reduced undermining and traditional abdominal skin flap resection. Aesthetic plastic surgery, 2006, 30.1: 1-8.