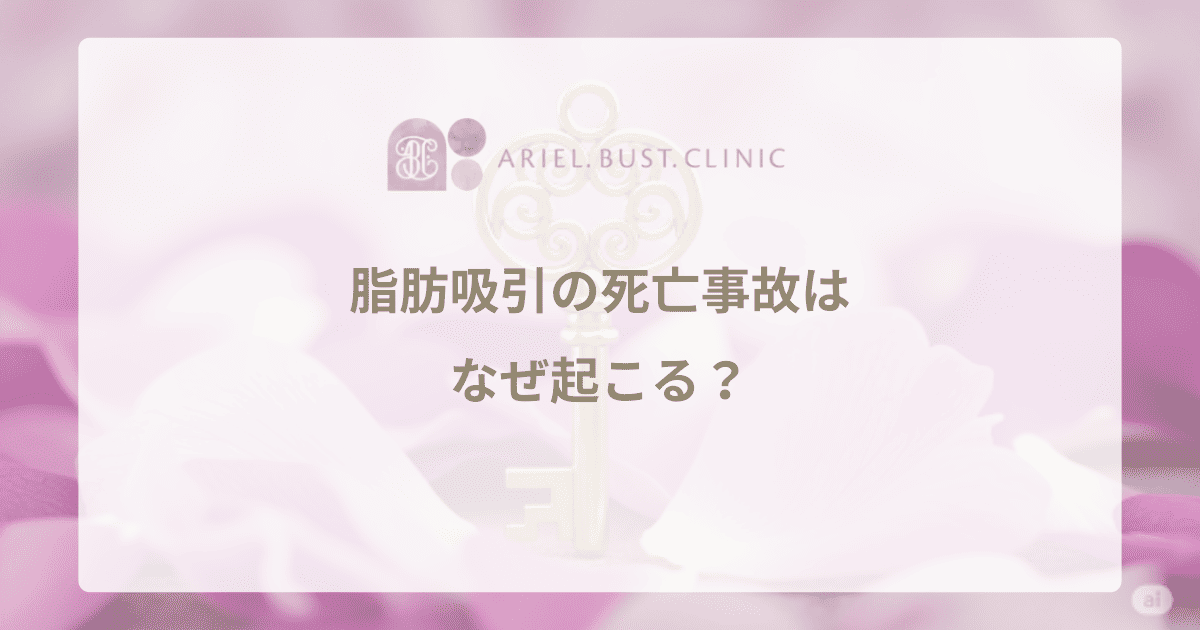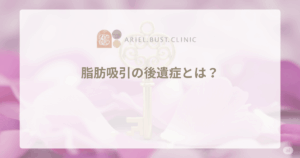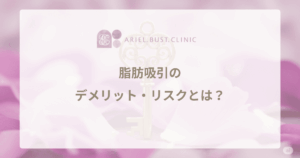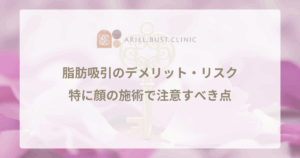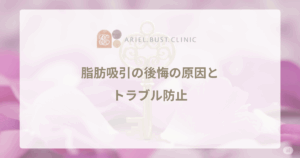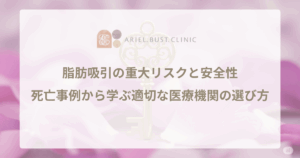脂肪吸引を検討する際、多くの方が「もしも」の事態を考え、死亡事故のリスクに不安を感じるのではないでしょうか。
インターネット上には様々な情報が溢れていますが、その信憑性を見極めるのは簡単ではありません。
この記事では、脂肪吸引における死亡事故がなぜ起こるのか、その原因と実際の死亡率について、医学的な観点から詳しく解説します。
そして、何よりも大切な「安全な手術を受けるために本当に重要なこと」を具体的にお伝えします。
この記事を読むことで、あなたの不安が解消され、冷静に、そして賢明に判断するための知識を得られるはずです。
資格・所属
- 日本形成外科学会専門医
- コンデンスリッチファット(CRF)療法認定医
- VASER Lipo認定医
- Juvederm Vista 認定医
- 乳房再建用エキスパンダー/インプラント実施医師
- 日本形成外科学会所属
- 日本美容外科学会(JSAPS)所属
【略歴】
脂肪吸引、豊胸を専門としている形成外科専門医。獨協医科大学医学部卒業後、獨協医科大学病院形成外科・美容外科入局。足利赤十字病院形成外科、獨協医科大学埼玉医療センター 形成外科学内助教、THE CLINIC大阪院・名古屋院の副院長を経て2024年、名古屋にARIEL .BUST.CLINICを開院。
ARIEL .BUST.CLINICは、脂肪吸引を得意とする名古屋のクリニックです。それぞれの体型や悩みに応じた専門性を活かしたご提案をしており、傷跡や傷のケアに形成外科専門医としての知識と技術を評価いただき、全国から患者様にお越しいただいています。
ボディメイクは決して焦る必要のないものです。このサイトでは脂肪吸引に関連する多くの記事を書いていますので、すぐに施術を決めることはせず、まずはぜひ患者様自身で知識をつけた上でご希望のクリニックへ相談されるようにしてください。
脂肪吸引の死亡事故は本当に起こるのか
「脂肪吸引で死亡事故」という言葉は、非常に衝撃的で、手術を考える人にとっては大きな不安材料です。まず、このリスクがどの程度現実的なものなのか、正しく理解することが大切です。
残念ながら、脂肪吸引による死亡事故は、国内外で実際に報告されており、決してゼロではありません。
脂肪吸引の死亡事故に関する報道
時折、ニュースなどで美容外科手術による死亡事故が報道されることがあります。脂肪吸引も例外ではなく、過去には日本国内でも死亡に至った事例が報じられています。
これらの報道は、手術の危険性を社会に警鐘を鳴らす一方で、情報が断片的であったり、過度に扇情的な内容であったりすることも少なくありません。
報道された事例の多くは、麻酔管理の不備や、医師の技術的な問題、術後の合併症への対応の遅れなどが原因として挙げられています。
国内外での事故事例の概要
海外に目を向けると、日本よりもはるかに多くの脂肪吸引手術が行われているため、それに比例して事故事例の報告も多くなります。
アメリカ形成外科学会(ASPS)などの専門機関は、事故事例を収集・分析し、原因を究明することで、より安全な手術方法の確立に努めています。
これらの分析から、死亡事故の主な原因は、肺塞栓症、腹部臓器の損傷、麻酔に関連する合併症などであることが分かっています。
事故事例から見る主な原因
| 原因の分類 | 具体的な内容 | 予防のために重要なこと |
|---|---|---|
| 合併症 | 肺塞栓症、脂肪塞栓症、重度の感染症など | 術後の経過観察、早期発見・早期治療 |
| 手術手技 | 内臓損傷、血管損傷、過度の出血など | 医師の技術力、解剖学の深い知識 |
| 麻酔管理 | 麻酔薬の過量投与、呼吸管理の不備など | 麻酔科専門医による管理、全身状態の監視 |
なぜ死亡事故の情報は少ないのか
死亡事故という重大な結果にもかかわらず、その情報が一般にあまり出回らないのには理由があります。一つは、医療機関側が情報を公にしたがらない傾向があることです。
また、患者側もプライバシーの問題から、公になることを望まないケースが多いでしょう。
さらに、美容医療は自由診療であり、公的な第三者機関による網羅的なデータ収集が、他の保険診療の分野ほど進んでいないという背景もあります。
美容医療におけるリスクの捉え方
どのような医療行為にも、リスクは伴います。脂肪吸引も例外ではありません。
大切なのは、リスクをゼロにすることではなく、リスクを正しく理解し、その可能性を限りなく低くするための対策が講じられているかを見極めることです。
そのためには、患者自身が正しい知識を持ち、信頼できる医療機関を選択する眼を養うことが重要になります。
脂肪吸引の死亡率に関するデータ
死亡事故のリスクを客観的に判断するためには、「死亡率」という具体的なデータが参考になります。しかし、この死亡率に関しても、正確な数値を把握するのは容易ではありません。
公的な統計データは存在するのか
現在、日本国内において、美容外科手術全体、あるいは脂肪吸引手術に限定した死亡率を網羅した、国による公式な統計データは存在しません。
これは前述の通り、美容医療が自由診療であることが大きな理由です。各医療機関や学会レベルでのデータ収集は行われていますが、全国的な統一された統計がないのが現状です。
海外の研究で報告されている死亡率
一方で、美容医療の研究が進んでいる米国などでは、脂肪吸引の死亡率に関する学術的な報告がいくつか存在します。
信頼性の高い研究報告によると、脂肪吸引の死亡率は、およそ「5万件に1件」から「10万件に1件」程度とされています。
この数値を高いと見るか、低いと見るかは人それぞれですが、決してゼロではないという事実は重く受け止める必要があります。
脂肪吸引の死亡率に関する海外報告
| 報告機関・研究者 | 報告された死亡率 | 備考 |
|---|---|---|
| Grazer & de Jong (2000) | 約5万件に1件 (19.1/100,000) | 複数の調査をまとめたレビュー論文 |
| Hughes (2008) | 約7万5千件に1件 (13/100,000) | 麻酔科医が関与した調査 |
| ASPS (米国形成外科学会) | 約10万件に1件以下 | 専門医による手術でのデータ |
死亡率に影響を与える要因
脂肪吸引の死亡率は、様々な要因によって変動します。例えば、一度に吸引する脂肪の量が多ければ多いほど、身体への負担は増大し、リスクは高まります。
また、腹部や胸部など、重要な臓器に近い部位の手術は、他の部位に比べて慎重な操作が求められます。患者自身の健康状態、年齢、肥満度などもリスクに影響を与える重要な要素です。
他の外科手術との死亡率比較
脂肪吸引のリスクを相対的に理解するために、他の一般的な外科手術の死亡率と比較してみましょう。
もちろん、手術の目的や対象となる患者層が異なるため、単純な比較はできませんが、一つの目安にはなります。
各種手術の死亡率(目安)
| 手術の種類 | 死亡率の目安 | 主なリスク |
|---|---|---|
| 脂肪吸引 | 5万〜10万件に1件 | 肺塞栓症、脂肪塞栓症 |
| 帝王切開(予定) | 約2万件に1件 | 出血、麻酔合併症 |
| 虫垂切除術 | 約1000件に1件 | 感染症、縫合不全 |
このように見ると、脂肪吸引の死亡率は、他の一般的な外科手術と比較して、際立って高いわけではないことが分かります。
しかし、脂肪吸引は生命維持に直接関わる治療ではなく、あくまで容姿を整えるための「選択的な手術」です。その点を踏まえ、より一層の安全性が求められます。
脂肪吸引で死亡事故が起こる主な原因
では、具体的にどのようなことが原因で、脂肪吸引は死亡という最悪の結果に至るのでしょうか。原因は大きく分けて「麻酔」「手術手技」「術後合併症」の3つに分類できます。
麻酔に関連するトラブル
脂肪吸引手術において、麻酔は痛みを取り除き、安全に手術を行うために必要です。しかし、その麻酔管理に不備があると、重大な事故につながる可能性があります。
全身麻酔と静脈麻酔のリスク
広範囲の脂肪吸引や、多くの脂肪を吸引する場合には、全身麻酔や静脈麻酔が用いられます。これらの麻酔方法は、患者の意識をなくし、呼吸や血圧などの全身状態に影響を与えます。
麻酔薬の量が多すぎたり、患者の体質に合わなかったりすると、呼吸抑制や血圧の急激な低下、アレルギー反応(アナフィラキシーショック)などを引き起こし、命に関わる事態になり得ます。
麻酔科医の不在
安全な麻酔管理のためには、麻酔に関する深い知識と経験を持つ麻酔科専門医の存在が極めて重要です。
手術を担当する外科医が麻酔も兼任する場合、手術操作に集中するあまり、患者の全身状態の変化に気づくのが遅れる危険性があります。
手術中は、執刀医とは別に、麻酔科医が常に患者のそばで呼吸、心拍、血圧などを監視し、万が一の事態に迅速に対応できる体制が理想です。
麻酔方法別のリスク比較
| 麻酔方法 | 特徴 | 主なリスク |
|---|---|---|
| 局所麻酔 | 意識は保たれたまま、手術部位のみ麻酔 | 麻酔薬中毒(過量投与時) |
| 静脈麻酔 | 点滴で麻酔薬を投与し、眠った状態にする | 呼吸抑制、血圧低下 |
| 全身麻酔 | 麻酔ガスや静脈麻酔薬で完全に意識をなくす | 呼吸・循環管理の合併症、アレルギー |
手術中の技術的な問題
執刀医の技術や経験不足が、直接的な事故原因となるケースもあります。脂肪層の下には、血管や神経、そして腹部であれば腸などの内臓があります。
これらの組織を傷つけないよう、正確に脂肪層だけを吸引する技術が求められます。
血管や内臓の損傷
脂肪吸引で用いるカニューレ(吸引管)の操作を誤ると、皮下の太い血管を傷つけて大量出血を引き起こしたり、腹壁を貫通して腸や肝臓などの内臓を損傷(穿孔)させたりする危険性があります。
特に腹部の脂肪吸引では、内臓損傷のリスクに細心の注意を払う必要があります。内臓損傷が起こると、腹膜炎という重篤な感染症を引き起こし、命に関わります。
カニューラの操作ミス
医師の経験不足や解剖学的な知識の欠如は、カニューラの不適切な操作につながります。
無理な力でカニューレを挿入したり、間違った層を吸引したりすることで、周辺組織へのダメージが大きくなり、予期せぬ合併症のリスクを高めます。
術後の合併症
手術が無事に終了しても、安心はできません。術後の経過中に発生する合併症が、死亡事故の最大の原因となることも少なくありません。特に注意すべきは「肺塞栓症」と「感染症」です。
肺塞栓症(エコノミークラス症候群)
脂肪吸引の死亡原因として最も報告が多いのが、肺塞栓症です。
これは、長時間同じ体勢でいることなどにより、足の静脈にできた血の塊(血栓)が、術後に体を動かした際に血流に乗って肺に達し、肺の血管を詰まらせてしまう病気です。
広範囲の脂肪吸引や、長時間の手術では、このリスクが高まります。突然の呼吸困難や胸の痛みが特徴で、迅速な対応がなければ死に至る危険性が高い合併症です。
- 長時間の手術
- 術後の安静
- 脱水状態
- 肥満
感染症と敗血症
手術創から細菌が侵入し、感染を起こすことがあります。
通常は抗生物質などで治療可能ですが、抵抗力が落ちている場合や、発見が遅れた場合には、細菌が血液中に入り込んで全身に広がる「敗血症」という危険な状態になることがあります。
敗血症は、多臓器不全などを引き起こし、致命的となる可能性があります。クリニックの衛生管理が徹底されているかどうかが、感染症予防の鍵となります。
脂肪塞栓症
非常に稀ですが、手術中に傷ついた血管から脂肪滴が血液中に入り込み、肺や脳の血管を詰まらせる「脂肪塞栓症」も報告されています。
これも肺塞栓症と同様に、呼吸困難や意識障害などを引き起こす重篤な合併症です。
死亡事故につながりやすい危険な脂肪吸引
すべての脂肪吸引が同じリスクを持つわけではありません。特定の条件下では、死亡事故につながるリスクが著しく高まることがあります。
以下のような手術計画には、特に注意が必要です。
一度に広範囲・大量の脂肪を吸引する手術
「一度で全身をすっきりさせたい」という希望を持つ方もいますが、一度の手術で吸引する脂肪の量や範囲には、安全上の限界があります。
一般的に、吸引量が5000mlを超える「大量吸引」は、出血量が多くなり、体液のバランスが崩れ、身体への負担が急激に増大します。
これにより、ショック状態に陥ったり、術後の回復が遅れたり、重篤な合併症のリスクが高まったりします。
吸引量とリスクの関係
| 吸引量の目安 | 分類 | リスクレベル |
|---|---|---|
| 〜3000ml | 通常量 | 比較的低い |
| 3000ml〜5000ml | 比較的多量 | 注意が必要 |
| 5000ml〜 | 大量吸引 | 高い |
他の美容外科手術との同時進行
脂肪吸引と同時に、骨切り手術や豊胸手術など、身体への負担が大きい他の手術を行うと、手術時間が長くなり、麻酔薬の使用量も増えます。
その結果、出血量の増加、血栓症のリスク増大、感染のリスク増大など、それぞれの単独手術のリスクが相乗的に高まる可能性があります。
複数の手術を同時に検討する場合は、それぞれの専門医が連携し、安全性を最優先した計画を立てることが重要です。
体力や健康状態を無視した手術計画
脂肪吸引は、健康な人が受けることを前提とした手術です。貧血、心臓や肺の病気、糖尿病、高血圧などの持病がある場合、手術や麻酔のリスクが高まります。
また、BMIが極端に高い高度肥満の方も、血栓症などのリスクが高いため、手術が適さない場合があります。
カウンセリングで自身の健康状態を正直に伝え、医師がリスクを正しく評価できる状況を作ることが大切です。
安全管理体制が不十分なクリニック
万が一の事態は、どんなに優れた医師が手術をしても起こり得ます。重要なのは、そうした事態が発生した際に、迅速かつ的確に対応できる体制が整っているかどうかです。
緊急時に対応できる医療機器(モニター類、除細動器、気管挿管セットなど)が整備されていない、あるいはスタッフがその使用方法に習熟していないクリニックでは、小さなトラブルが大きな事故につながりかねません。
安全な脂肪吸引を受けるためのクリニック選び
脂肪吸引の安全性を高めるために、患者自身ができる最も重要なことは「信頼できるクリニックを選ぶこと」です。
価格の安さや広告のイメージだけで選ぶのではなく、以下のポイントをしっかりと確認しましょう。
医師の経歴と専門性の確認
脂肪吸引は医師の技術力と経験が結果と安全性に直結します。医師の経歴は、その信頼性を測る上での重要な指標です。
形成外科専門医や美容外科専門医の資格
「形成外科専門医」や「美容外科専門医(JSAPS、JSAS)」といった資格は、一定期間のトレーニングを受け、厳しい試験に合格した医師にのみ与えられます。
これらの資格は、医師が持つ技術や知識レベルを客観的に示す一つの基準となります。クリニックのウェブサイトなどで、担当医師がこれらの資格を保有しているか確認しましょう。
医師の専門資格の例
| 資格名 | 認定団体 | 意味すること |
|---|---|---|
| 日本形成外科学会 形成外科専門医 | 日本形成外科学会 | 形成外科領域全般の知識と技術を証明 |
| 日本美容外科学会(JSAPS)専門医 | 日本美容外科学会 | 美容外科領域の高い専門性を証明 |
| 日本美容外科学会(JSAS)専門医 | 日本美容外科学会 | 美容外科領域の臨床経験と知識を証明 |
脂肪吸引の症例数と経験
専門医資格に加えて、その医師がどれだけ脂肪吸引の手術を経験してきたかも重要です。
多くの症例を経験している医師は、様々なケースに対応する能力が高く、予期せぬ事態にも冷静に対処できる可能性が高いと言えます。
カウンセリングの際に、具体的な症例数や、自身と似たケースの写真などを見せてもらうと良いでしょう。
カウンセリングの質
カウンセリングは、手術に関する情報を得るだけでなく、医師やクリニックの姿勢を見極めるための重要な機会です。
リスク説明の丁寧さ
良いクリニックは、手術のメリットだけでなく、デメリットやリスク、合併症の可能性について、時間をかけて丁寧に説明します。
死亡事故のような最悪のケースについても、隠さずにきちんと説明し、それに対する安全対策を具体的に示してくれる医師は信頼できます。
逆に、良いことばかりを強調し、リスクの説明を怠るようなクリニックは注意が必要です。
- 合併症の種類
- 発生頻度
- 発生時の対応
- 後遺症の可能性
患者の希望と懸念への対応
あなたの希望や不安、疑問に対して、親身に耳を傾け、納得できるまで説明してくれるかどうかも大切なポイントです。
一方的に手術を勧めるのではなく、あなたの体質やライフスタイルを考慮した上で、最適な方法を一緒に考えてくれる医師を選びましょう。
クリニックの安全管理体制
医師の技術力だけでなく、クリニック全体の安全管理体制も必ず確認すべき項目です。
麻酔科専門医の常駐
特に全身麻酔や静脈麻酔を用いる手術の場合、日本麻酔科学会が認定する「麻酔科専門医」や「麻酔科標榜医」が手術に立ち会う体制が整っているかを確認しましょう。
麻酔科医が常駐しているクリニックは、安全管理に対する意識が高いと言えます。
緊急時対応設備の有無
万が一、手術中に容態が急変した場合に備えて、どのような医療機器が備えられているかを確認することも重要です。
心電図や血圧計などの生体情報モニターはもちろん、AED(自動体外式除細動器)や救急蘇生薬、近隣の高度医療機関との連携体制などが整っていると、より安心です。
衛生管理の徹底
術後の感染症を防ぐためには、手術室の清潔さや、使用する器具の滅菌処理が徹底されていることが大前提です。
カウンセリングの際に、院内の清掃状況や衛生管理に関する取り組みについて質問してみるのも良いでしょう。
手術前に患者自身ができること
安全な手術は、クリニック側だけの努力で成り立つものではありません。患者自身も、自分の体を守るために、積極的に協力することが重要です。
自身の健康状態の正確な申告
カウンセリングや問診では、自身の健康状態について、正確に、そして正直に伝える義務があります。些細なことだと思っても、それが手術の安全性に大きく影響することがあります。
既往歴やアレルギー、服用中の薬
過去にかかった病気(特に心臓、肺、肝臓、腎臓の病気)、アレルギーの有無(薬、食物など)、現在服用している薬やサプリメントは、すべて医師に伝えましょう。
特に、血液をサラサラにする薬(抗凝固薬)などを服用している場合は、手術中の出血リスクが高まるため、事前の休薬などが必要です。
申告すべき健康情報
| 項目 | 具体例 | なぜ重要か |
|---|---|---|
| 既往歴 | 心疾患、呼吸器疾患、糖尿病、高血圧 | 麻酔や手術のリスク評価に必要 |
| アレルギー | 薬剤、麻酔薬、消毒薬、ラテックス | アレルギー反応(ショック)の予防 |
| 服用薬 | 抗凝固薬、サプリメント、漢方薬 | 出血傾向や薬の相互作用を避けるため |
喫煙や飲酒の習慣
喫煙は、血管を収縮させて血流を悪くし、傷の治りを遅らせたり、感染症や血栓症のリスクを高めたりします。安全な手術のためには、術前から禁煙することが強く推奨されます。
飲酒習慣についても、肝機能への影響などを考慮する必要があるため、正直に申告しましょう。
無理のない手術計画の選択
医師から複数の選択肢を提示された場合、リスクと効果のバランスをよく考え、無理のない計画を選びましょう。
一度に多くの脂肪を吸引するよりも、複数回に分けて手術を行う方が、体への負担は少なく、安全性は高まります。
「早く終わりたい」という気持ちだけで、リスクの高い方法を選択することは避けるべきです。
セカンドオピニオンの活用
一つのクリニックの説明だけで手術を決めることに不安がある場合は、ためらわずに他のクリニックでセカンドオピニオンを求めましょう。
複数の専門家の意見を聞くことで、より客観的に状況を判断でき、自分にとって最善の選択ができるようになります。
術後のセルフケアに関する理解
手術後の過ごし方も、合併症の予防には非常に重要です。医師や看護師から指示された注意点(圧迫固定の着用、薬の服用、安静度、術後の検診など)をしっかりと守りましょう。
特に、肺塞栓症の予防のためには、術後早期から無理のない範囲で体を動かすことが大切です。
脂肪吸引の死亡事故に関するよくある質問
最後に、脂肪吸引の死亡リスクに関して、多くの方が抱く疑問についてお答えします。
- 脂肪吸引で最も危険な部位はどこですか?
-
一概に「この部位が最も危険」と断定することは難しいですが、一般的には、重要な臓器が集中している「腹部」や、太い血管や神経が走行している「太ももの付け根周辺」などは、特に慎重な手技が求められる部位です。
腹部の手術では内臓損傷のリスクが、太ももの手術では血管損傷や血栓症のリスクが相対的に高いと考えられます。
しかし、どの部位であっても、医師の技術と知識が伴っていれば、安全に手術を行うことは可能です。
- 日帰り手術でも死亡リスクはありますか?
-
はい、日帰り手術であっても死亡リスクがゼロになるわけではありません。肺塞栓症などの重篤な合併症は、手術から数日経ってから発症することもあります。
そのため、日帰り手術であっても、術後の経過観察が非常に重要です。
帰宅後に何か異変を感じた際に、すぐにクリニックと連絡が取れるか、夜間や休日の緊急連絡体制が整っているかなどを、事前に確認しておくことが大切です。
- 術後に異変を感じた場合の対処法を教えてください
-
術後に以下のような症状が現れた場合は、自己判断で様子を見たりせず、直ちに手術を受けたクリニックに連絡してください。
- 突然の息切れ、呼吸困難、胸の痛み
- 経験したことのないような足のむくみや痛み
- 38度以上の高熱が続く
- 手術創の赤み、腫れ、痛みが悪化する
これらの症状は、肺塞栓症や重度の感染症など、命に関わる合併症のサインである可能性があります。
夜間や休日であっても、ためらわずに緊急連絡先に連絡し、指示を仰ぐことが重要です。
- クリニックが万が一の事態に備えて保険に加入しているか確認すべきですか?
-
はい、確認することをお勧めします。多くのまともな美容クリニックは、医療事故に備えて「医師賠償責任保険」に加入しています。
これは、クリニックの安全意識の高さを示す一つの指標にもなります。保険への加入は、万が一の事態が起こった際に、患者が適切な補償を受けるための備えでもあります。
カウンセリングの際に、こうした補償制度について質問してみても良いでしょう。
安全対策の最終チェックリスト
確認項目 チェックポイント なぜ重要か 医師の専門性 形成外科や美容外科の専門医資格があるか 技術と知識レベルの客観的な証明 麻酔体制 麻酔科専門医が立ち会うか 麻酔中の全身管理の安全性を高める 緊急時対応 救急設備や連携病院が確保されているか 万が一の事態への備え カウンセリング リスク説明が十分で、質問しやすいか 納得して手術に臨むために必要
脂肪吸引は、正しく行われれば、理想のボディラインを手に入れることができる素晴らしい手術です。しかし、その裏には重大なリスクも潜んでいることを決して忘れてはいけません。
この記事で得た知識をもとに、慎重に、そして賢明に判断し、安全で満足のいく結果を手に入れてください。
参考文献
BEZERRA, Thiago Augusto Rochetti, et al. THE CLINICAL FINDINGS IN COMPLICATIONS AND DEATHS FROM LIPOSUCTION. Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences, 2024, 6.11: 1606-1622.
KAOUTZANIS, Christodoulos, et al. Cosmetic liposuction: preoperative risk factors, major complication rates, and safety of combined procedures. Aesthetic surgery journal, 2017, 37.6: 680-694.
CÁRDENAS-CAMARENA, Lázaro, et al. Strategies for reducing fatal complications in liposuction. Plastic and Reconstructive Surgery–Global Open, 2017, 5.10: e1539.
LEHNHARDT, Marcus, et al. Major and lethal complications of liposuction: a review of 72 cases in Germany between 1998 and 2002. Plastic and reconstructive surgery, 2008, 121.6: 396e-403e.
DILLERUD, Erik. Abdominoplasty combined with suction lipoplasty: a study of complications, revisions, and risk factors in 487 cases. Annals of plastic surgery, 1990, 25.5: 333-343.
COMERCI, Alexander J., et al. Risks and complications rate in liposuction: a systematic review and meta-analysis. Aesthetic Surgery Journal, 2024, 44.7: NP454-NP463.
WANG, Hui-Dong, et al. Fat embolism syndromes following liposuction. Aesthetic plastic surgery, 2008, 32.5: 731-736.
NOGUEIRA, FELIPE DE VILHENA MORAES, et al. Liposuction and fat embolism: a literature review. Revista Brasileira de Cirurgia Plástica, 2023, 30: 291-294.
ELGOHARY, Doaa; NADEEM, Rashid. Pulmonary Embolism Associated with Major Liposuction: A Case Report. Dubai Medical Journal, 2023, 6.4: 306-309.
RAO, Rama B.; ELY, Susan F.; HOFFMAN, Robert S. Deaths related to liposuction. New England Journal of Medicine, 1999, 340.19: 1471-1475.