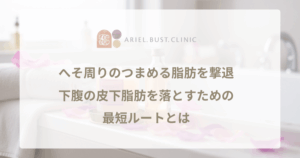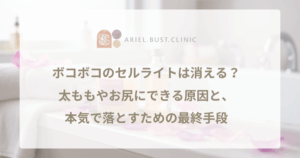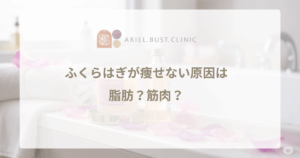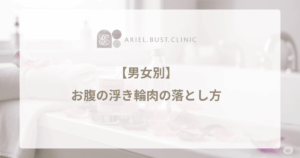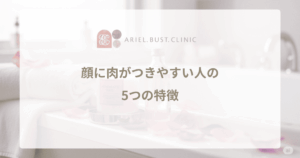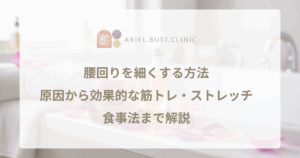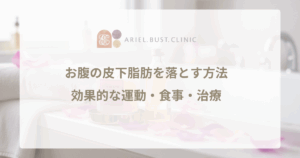ふと鏡を見たときや、写真に写った自分の姿を見て、「顎下の肉が気になる…」と感じたことはありませんか。
一度ついてしまうとなかなか落ちにくい顎下の脂肪は、顔が大きく見えたり、老けた印象を与えたりする原因になります。
この記事では、多くの人が悩む顎下の肉がついてしまう原因を詳しく解説します。
さらに、即効性が期待できるセルフケアとして、自宅で簡単にできるマッサージやエクササイズ、生活習慣の改善点まで、幅広く紹介します。
すっきりとしたフェイスラインを手に入れて、自信に満ちた毎日を送りましょう。
資格・所属
- 日本形成外科学会専門医
- コンデンスリッチファット(CRF)療法認定医
- VASER Lipo認定医
- Juvederm Vista 認定医
- 乳房再建用エキスパンダー/インプラント実施医師
- 日本形成外科学会所属
- 日本美容外科学会(JSAPS)所属
【略歴】
脂肪吸引、豊胸を専門としている形成外科専門医。獨協医科大学医学部卒業後、獨協医科大学病院形成外科・美容外科入局。足利赤十字病院形成外科、獨協医科大学埼玉医療センター 形成外科学内助教、THE CLINIC大阪院・名古屋院の副院長を経て2024年、名古屋にARIEL .BUST.CLINICを開院。
ARIEL .BUST.CLINICは、脂肪吸引を得意とする名古屋のクリニックです。それぞれの体型や悩みに応じた専門性を活かしたご提案をしており、傷跡や傷のケアに形成外科専門医としての知識と技術を評価いただき、全国から患者様にお越しいただいています。
ボディメイクは決して焦る必要のないものです。このサイトでは脂肪吸引に関連する多くの記事を書いていますので、すぐに施術を決めることはせず、まずはぜひ患者様自身で知識をつけた上でご希望のクリニックへ相談されるようにしてください。
そもそも顎下の肉がついてしまうのはなぜ?主な原因を解説
すっきりとしたフェイスラインの邪魔をする顎下の肉。なぜこの部分に肉がつきやすいのでしょうか。その原因は一つではなく、複数の要因が絡み合っていることが多いです。
ここでは、顎下の肉がついてしまう主な原因を4つに分けて詳しく見ていきましょう。
自分の生活習慣と照らし合わせながら、原因を探ることが、効果的な「顎 下 脂肪 落とし方」の第一歩です。
肥満による脂肪の蓄積
最も分かりやすい原因は、体全体の脂肪増加、つまり肥満です。食事で摂取するカロリーが、運動などで消費するカロリーを上回ると、余ったエネルギーは脂肪として体に蓄積します。
顔周り、特に顎下は脂肪がつきやすい部位の一つです。一度脂肪がついてしまうと、他の部位に比べて落ちにくいと感じる人も少なくありません。
体重が増加傾向にある人は、まずこの原因を疑ってみる必要があります。
加齢によるたるみ
年齢を重ねると、肌のハリや弾力を保つコラーゲンやエラスチンが減少し、皮膚がたるみやすくなります。また、顔の筋肉(表情筋)や、首の前側にある広頸筋(こうけいきん)という筋肉も衰えてきます。
これらの筋肉が衰えると、皮膚や皮下脂肪を支える力が弱まり、重力に負けて顎下がたるんでしまうのです。
体重は変わっていないのに、以前より顎下のラインがぼやけてきたと感じる場合は、加齢によるたるみが大きな原因であると考えられます。
姿勢の悪さ
長時間のデスクワークやスマートフォンの使用は、知らず知らずのうちに姿勢を悪くします。特に、猫背やストレートネックのように首が前に出る姿勢は、顎下の肉がつく大きな原因です。
頭は非常に重く、前に傾くだけで首や肩に大きな負担がかかります。この状態が続くと、首周りの血行が悪くなり、脂肪や老廃物が溜まりやすくなります。
また、常に顎を引いたような姿勢になるため、顎下の皮膚がたるんで二重顎を定着させてしまいます。
主な原因とその特徴
| 原因 | 主な特徴 | セルフケアの方向性 |
|---|---|---|
| 肥満 | 体重増加とともに出てくる。顎下を指でつまむと厚い脂肪が掴める。 | 食事管理、有酸素運動 |
| 加齢によるたるみ | 体重は変わらないのに目立つ。皮膚にハリがなく、下を向くとたるみが顕著になる。 | 表情筋エクササイズ、保湿ケア |
| 姿勢の悪さ | 猫背やストレートネックの人に多い。首や肩のこりも併発しやすい。 | 姿勢矯正、ストレッチ |
むくみ
塩分の多い食事やアルコールの摂取、睡眠不足などは、体のむくみを引き起こします。顔周りは特にむくみが出やすい部位であり、顎下も例外ではありません。
体内の余分な水分や老廃物がリンパの流れの滞りによって排出されずに溜まることで、フェイスラインがぼやけて見えます。
朝起きた時に顔がパンパンに感じたり、夕方になると靴がきつくなったりする人は、顎下の肉もむくみが原因である可能性が高いです。
むくみは一時的なものですが、慢性化すると脂肪の蓄積やたるみにつながることもあります。
【セルフチェック】あなたの顎下についた肉のタイプは?
顎下の肉を効果的にすっきりさせるためには、まず自分のタイプを知ることが重要です。原因が異なれば、取るべき対策も変わってきます。
ここでは、簡単なセルフチェック方法を紹介しますので、自分の顎下の肉がどのタイプに当てはまるか確認してみましょう。
脂肪タイプの特徴と見分け方
脂肪タイプは、その名の通り脂肪の蓄積が主な原因です。比較的若い世代にも多く見られます。以下の方法でチェックしてみましょう。
まず、姿勢を正して正面を向き、顎下の肉を親指と人差し指でつまんでみてください。指でしっかりと厚みがつまめる場合、それは皮下脂肪である可能性が高いです。
特に、2cm以上の厚みがつまめるようであれば、脂肪タイプと判断して良いでしょう。このタイプは、体全体のダイエットと並行して顎下へのアプローチを行うことが効果的です。
たるみタイプの特徴と見分け方
たるみタイプは、加齢や表情筋の衰えが原因です。体重は標準でも、フェイスラインがぼんやりしている人に多く見られます。
チェック方法は、まず正面を向いた状態で顎下の状態を確認します。次に、顔を真上に向け、天井と顔が平行になるようにしてみてください。
このとき、顎下の肉が目立たなくなり、すっきりとするようであれば、たるみタイプです。
皮膚や筋肉が重力に負けて垂れ下がっている証拠なので、表情筋を鍛えるエクササイズや、肌のハリをケアすることが有効です。
むくみタイプの特徴と見分け方
むくみタイプは、体内の水分バランスの乱れが原因です。日によって状態が変化するのが特徴です。
朝起きた時と夕方で、顎下のすっきり感が違うと感じる人は、むくみタイプの可能性があります。
また、顎下の肉を指で数秒間押してみてください。指を離したときに、跡が白く残り、なかなか元に戻らない場合もむくみが考えられます。
このタイプは、リンパマッサージや食生活の見直しが効果的です。
タイプ別セルフチェック法
| タイプ | チェック方法 | 主な特徴 |
|---|---|---|
| 脂肪タイプ | 顎下の肉を指でつまむ | 厚い脂肪がしっかりつまめる |
| たるみタイプ | 顔を真上に向ける | 上を向くと顎下の肉が目立たなくなる |
| むくみタイプ | 指で押して跡が残るか確認 | 日によって状態が変わり、指の跡が残りやすい |
複合タイプも多い
実際には、これらのタイプが単独で存在するだけでなく、「脂肪とたるみ」「たるみとむくみ」のように、複数の原因が組み合わさっている「複合タイプ」の人も非常に多いです。
例えば、肥満でついた脂肪の重みで皮膚がたるんでしまったり、姿勢の悪さで血行不良になり、むくみと脂肪蓄積の両方を引き起こしたりします。
自分のタイプが一つに絞れない場合は、複数のケアを組み合わせて行うことが、顎下の肉を落とすための近道になります。
自宅でできる!顎下の脂肪にアプローチするマッサージ
顎下の肉、特にむくみや滞った老廃物が原因の場合、マッサージは非常に効果的です。血行やリンパの流れを促進し、すっきりとしたフェイスラインを目指しましょう。
ここでは、自宅で簡単にできるマッサージ方法を紹介します。肌への摩擦を避けるため、必ずオイルやクリームを使って滑りを良くしてから行ってください。
リンパの流れを促す基本マッサージ
まずは、顔周りの老廃物を排出するための通り道であるリンパ節をほぐすことから始めます。これにより、後に行うマッサージの効果が高まります。
最初に、耳の下にある耳下腺リンパ節を、人差し指、中指、薬指の3本の指の腹で優しくクルクルと回すようにほぐします。
次に、そこから首筋を通って鎖骨の中心にある鎖骨リンパ節に向かって、指で優しくなで下ろします。この動作を5回ほど繰り返しましょう。
力は入れすぎず、心地よいと感じる程度の圧で行うのがポイントです。
顎のラインをシャープにするマッサージ
次に、顎下に直接アプローチしていきます。このマッサージは、フェイスラインのもたつきを解消するのに役立ちます。
両手でげんこつを作り、人差し指の第二関節を使います。顎の先端の骨の下に指を当て、そこから耳の下に向かって、フェイスラインに沿って少し圧をかけながらゆっくりと引き上げます。
これを左右同時に、5〜10回繰り返します。痛みを感じるほど強くこするのは避けましょう。
マッサージのポイント
| マッサージ名 | 主な目的 | 注意点 |
|---|---|---|
| 基本マッサージ | リンパの流れを促進 | 力を入れすぎない |
| 顎ラインマッサージ | フェイスラインの引き締め | 骨に沿ってゆっくり行う |
| 首周りのマッサージ | こりの解消、血行促進 | 皮膚を引っ張らない |
首周りのこりをほぐすマッサージ
顎下の肉は、首や肩のこりとも密接な関係があります。首周りの筋肉をほぐすことで、血行が良くなり、顔周りの老廃物が流れやすくなります。
片方の手のひら全体を、反対側の首筋(耳の下から肩にかけて)に当てます。そして、肩に向かって優しくなで下ろします。これを左右それぞれ5回ずつ行います。
次に、首の後ろに両手を組み、親指で首の骨の両脇を優しく押して刺激します。これにより、長時間のデスクワークなどでこり固まった首の筋肉がほぐれます。
マッサージを行う際の注意点
セルフマッサージは手軽で効果的ですが、やり方を間違えると肌トラブルの原因になることもあります。以下の点に注意して行いましょう。
- 必ずオイルやクリームを使用する
- 力を入れすぎず、優しい圧で行う
- 肌に赤みや痛みが出た場合は中止する
- 体調が優れない時や、肌荒れしている時は避ける
これらの注意点を守り、毎日続けることで、顎下のすっきり感を実感しやすくなります。お風呂上がりなど、血行が良くなっている時に行うのが特におすすめです。
顎下のたるみを引き締める!即効性が期待できるエクササイズ
たるみが原因で顎下の肉が目立つ場合、マッサージと合わせて行いたいのが表情筋のエクササイズです。
顔や首周りの筋肉は、普段の生活ではあまり使われない部分も多く、意識して動かすことで効果的に引き締めることができます。
ここでは、道具を使わずにできる簡単なエクササイズを紹介します。継続することが「顎 下 脂肪 落とし方」の鍵です。
「あいうえお」体操で表情筋を鍛える
口周りや頬の筋肉を大きく動かすことで、顔全体の血行を促進し、たるみをケアする基本的なエクササイズです。
まず、口をできるだけ大きく開けて「あ」の形を作ります。次に、口を横に大きく引いて「い」。唇を前に突き出して「う」。口角をしっかり上げて「え」。最後に、口を縦に大きく開けて「お」。
それぞれの形を5秒ずつキープしながら、ゆっくりと行います。これを1セットとして、1日に3セット程度行うのがおすすめです。
上を向いて舌を出すエクササイズ
このエクササイズは、顎下から首にかけての筋肉(広頸筋)を直接刺激し、二重顎の解消に高い効果が期待できます。
椅子に座るか立った状態で、姿勢を正します。次に、ゆっくりと顔を上げて天井を見ます。そのまま、舌を天井に向かってできるだけ遠くに、まっすぐ突き出します。
この状態で10秒間キープします。舌をゆっくりと戻し、顔も正面に戻します。この動作を3〜5回繰り返しましょう。首を痛めないように、ゆっくり行うことが大切です。
おすすめエクササイズと頻度の目安
| エクササイズ | 鍛えられる部位 | 1日の目安 |
|---|---|---|
| 「あいうえお」体操 | 表情筋全体 | 3セット |
| 舌出しエクササイズ | 顎下、広頸筋 | 3〜5回 |
| ペットボトルトレーニング | 口輪筋 | 10秒キープを3回 |
ペットボトルを使った簡単トレーニング
口周りの筋肉(口輪筋)を鍛えることで、顔の下半分のたるみを防ぎます。口輪筋は他の表情筋とも繋がっているため、ここを鍛えることは顔全体の引き締めにつながります。
500mlの空のペットボトルを用意します。中に少量の水(50ml程度から始めるのがおすすめ)を入れます。そして、歯を使わずに唇だけでペットボトルをくわえ、ゆっくりと持ち上げます。
そのまま10秒間キープし、ゆっくりと下ろします。これを3回繰り返します。慣れてきたら、水の量を少しずつ増やして負荷を調整しましょう。
エクササイズを継続するコツ
これらのエクササイズは、一度行っただけですぐに効果が出るものではありません。大切なのは、毎日少しずつでも継続することです。
洗面所に立ったついでや、テレビを見ながらなど、生活の中に組み込んで習慣化するのがおすすめです。「ながら」で行えるエクササイズも多いので、無理なく続けられる方法を見つけましょう。
数週間続けることで、フェイスラインの変化を感じられるはずです。
普段の生活で見直したい!顎下の肉を増やさないための習慣
マッサージやエクササイズで顎下の肉にアプローチしても、普段の生活習慣が原因のままでは、なかなか効果が出にくく、元に戻ってしまう可能性があります。
すっきりとしたフェイスラインを維持するためには、日々の習慣を見直すことが重要です。ここでは、顎下の肉を増やさないために意識したい4つのポイントを紹介します。
正しい姿勢を意識する
姿勢の悪さ、特に猫背やストレートネックは顎下の肉の大きな原因です。デスクワーク中やスマートフォンを見ている時など、無意識に頭が前に出ていないかチェックしましょう。
正しい姿勢は、耳、肩、腰が一直線になる状態です。壁に背中とかかとをつけて立ち、後頭部が自然に壁につくか確認するのも良い方法です。
日頃から背筋を伸ばし、顎を軽く引くことを意識するだけで、首への負担が減り、フェイスラインがすっきりします。
姿勢改善のチェックポイント
| 場面 | 悪い姿勢の例 | 改善のポイント |
|---|---|---|
| デスクワーク | 画面を覗き込むように首が前に出る | モニターを目線の高さに合わせる |
| スマホ操作 | 下を向いて長時間操作する | スマホを顔の高さまで上げて操作する |
| 歩行時 | 猫背でうつむき加減に歩く | 頭のてっぺんから糸で吊られているイメージを持つ |
食生活の改善ポイント
顎下の脂肪やむくみは、食生活と深く関わっています。まず、脂肪の蓄積を防ぐためには、バランスの取れた食事が基本です。
揚げ物やスナック菓子などの脂質、甘いものの糖質を摂りすぎないように注意し、タンパク質や野菜、果物を積極的に取り入れましょう。
また、むくみ対策としては、塩分の排出を助けるカリウム(海藻類、バナナ、ほうれん草など)を意識して摂ることが有効です。
食事はよく噛んで食べることも、顎周りの筋肉を使うことにつながり、引き締め効果が期待できます。
食事で意識したい栄養素
- タンパク質(筋肉や肌の材料)
- ビタミンC(コラーゲン生成を助ける)
- カリウム(余分な塩分を排出)
- 食物繊維(腸内環境を整える)
スマートフォンの使い方を見直す
現代人にとって、スマートフォンは顎下の肉を作る大きな要因の一つです。「スマホ首」とも呼ばれるストレートネックは、長時間うつむいた姿勢で画面を見続けることで引き起こされます。
この姿勢は、顎下の皮膚をたるませ、二重顎を定着させるだけでなく、血行不良によるむくみや脂肪の蓄積も招きます。
スマートフォンを使う際は、できるだけ顔の高さまで上げて持つように意識し、30分に一度は休憩して首周りをストレッチするなど、使い方を工夫することが大切です。
質の良い睡眠を確保する
睡眠不足は、体の代謝を低下させ、脂肪を燃焼しにくくします。また、ホルモンバランスの乱れから食欲が増し、太りやすくなることも分かっています。
さらに、睡眠の質が低いと、体の回復が十分に行われず、むくみや肌のたるみにもつながります。毎日6〜8時間程度の睡眠時間を確保するよう心がけましょう。
寝る前のスマートフォン操作やカフェイン摂取を避ける、自分に合った高さの枕を使うなど、睡眠の質を高める工夫も、巡り巡って顎下の肉を落とすことにつながります。
マッサージやエクササイズの効果を高めるサポートアイテム
セルフケアをより効果的にするために、便利なサポートアイテムを活用するのも一つの方法です。マッサージやエクササイズと組み合わせることで、相乗効果が期待できます。
ここでは、手軽に取り入れられるアイテムとその活用法を紹介します。自分に合ったものを見つけて、日々のケアに取り入れてみましょう。
マッサージオイル・クリームの選び方
マッサージを行う際には、肌への摩擦を軽減し、滑りを良くするためにオイルやクリームが必須です。
保湿成分(ヒアルロン酸、セラミドなど)が豊富に含まれているものを選ぶと、マッサージしながらスキンケアもできます。
また、引き締め効果が期待できる成分(カフェイン、ショウガエキスなど)や、リラックス効果のある香りのものを選ぶのもおすすめです。自分の肌質や好みに合わせて選びましょう。
おすすめの成分
| 目的 | 成分例 | 期待できる効果 |
|---|---|---|
| 保湿 | ヒアルロン酸、セラミド | 肌の潤いを保ち、乾燥を防ぐ |
| 引き締め | カフェイン、ショウガエキス | 肌にハリを与え、すっきりさせる |
| リラックス | ラベンダー、カモミール | 香りで心身をリラックスさせる |
美顔ローラーの活用法
手軽にマッサージができる美顔ローラーは、顎下のケアにも有効なアイテムです。特にY字型のローラーは、フェイスラインを挟み込むようにして使えるため、顎下にフィットしやすいのが特徴です。
使い方は簡単で、顎の先端から耳の下に向かって、フェイスラインに沿って優しくコロコロと転がすだけです。マッサージクリームなどを塗った後に行うと、よりスムーズにケアできます。
ただし、やりすぎは肌への負担になるため、1日数分程度にとどめましょう。
フェイスマスクで保湿と引き締め
エクササイズやマッサージ後のスペシャルケアとして、フェイスマスクを取り入れるのも良いでしょう。特に、顎下までしっかりとカバーできるリフトアップタイプのマスクがおすすめです。
シートに含まれた美容成分が肌に浸透し、潤いとハリを与えます。耳にかけるタイプのマスクは、物理的に肌を引き上げる効果も期待でき、使用後はフェイスラインがすっきりとした印象になります。
週に1〜2回の定期的な使用が効果的です。
サポートアイテムの選び方のポイント
- 自分の肌質に合ったものを選ぶ
- 継続して使いやすい価格帯のものを選ぶ
- 使用方法や頻度を守って使う
サプリメントは補助的に
体の内側からのケアとして、サプリメントを検討する人もいるかもしれません。
例えば、むくみが気になる人向けのカリウムや、肌のハリをサポートするコラーゲン、代謝を助けるビタミンB群などがあります。
しかし、サプリメントはあくまで食事を補助するものです。まずはバランスの取れた食事を基本とし、それでも不足しがちな栄養素を補うという位置づけで活用するのが賢明です。
サプリメントだけで顎下の肉が落ちるわけではないことを理解しておきましょう。
それでも改善しない場合は?美容医療という選択肢
セルフケアを長期間続けても、なかなか満足のいく結果が得られない場合や、より早く効果を実感したい場合には、美容医療に頼るという選択肢もあります。
近年、メスを使わずに顎下の脂肪やたるみにアプローチできる施術が増えています。
ここでは代表的な施術をいくつか紹介しますが、実際に受ける際は必ず専門のクリニックでカウンセリングを受け、医師の説明を十分に理解することが重要です。
脂肪溶解注射
脂肪溶解注射は、脂肪を溶かす作用のある薬剤を、気になる部分に直接注入する施術です。顎下のような部分的な脂肪に効果的で、溶かされた脂肪は老廃物として体外に排出されます。
ダウンタイムが比較的短く、注射のみで終わるため手軽に受けやすいのが特徴です。効果を実感するまでには数回の施術が必要な場合があります。
糸リフト
糸リフト(スレッドリフト)は、医療用の特殊な糸を皮下に挿入し、たるんだ皮膚を物理的に引き上げる施術です。加齢によるたるみが主な原因で顎下のラインが崩れている場合に高い効果を発揮します。
また、糸を挿入した刺激でコラーゲンの生成が促進され、肌のハリがアップする効果も期待できます。効果の持続期間は糸の種類によって異なります。
ハイフ(HIFU)
ハイフは、高密度の超音波エネルギーを皮膚の深い層(SMAS筋膜)に照射し、熱で組織を収縮させることでたるみを引き上げる施術です。
メスや注射を使わずにリフトアップ効果が得られるため、人気の高い治療法の一つです。
顎下やフェイスラインの引き締めに効果的で、施術直後から効果を感じる人もいますが、数ヶ月かけてさらに引き締まっていきます。
代表的な美容医療の比較
| 施術名 | 主な対象 | 特徴 |
|---|---|---|
| 脂肪溶解注射 | 脂肪タイプ | 部分的な脂肪を注射で溶かす |
| 糸リフト | たるみタイプ | 糸で物理的にたるみを引き上げる |
| ハイフ(HIFU) | たるみタイプ | 超音波で皮膚の深い層から引き締める |
美容医療を受ける前に知っておくべきこと
美容医療は効果が期待できる一方で、リスクや副作用が全くないわけではありません。また、費用もセルフケアに比べて高額になります。
施術を受ける前には、必ず信頼できるクリニックを選び、経験豊富な医師によるカウンセリングを受けることが大切です。
期待できる効果だけでなく、ダウンタイム、リスク、費用についてもしっかりと説明を受け、納得した上で施術を決めるようにしましょう。
複数のクリニックでカウンセリングを受けて比較検討することも重要です。
よくある質問
最後に、顎下の肉に関して多くの人が抱く疑問についてお答えします。セルフケアを始める前や、続けている中での不安解消に役立ててください。
- 顎下の肉はどれくらいの期間で落ちますか?
-
効果を実感できるまでの期間は、原因やケアの方法、個人の体質によって大きく異なります。
むくみが原因の場合は、マッサージや食生活の改善で数日から1週間程度で変化を感じることもあります。しかし、脂肪やたるみが原因の場合は、より長期間の継続的なケアが必要です。
エクササイズや生活習慣の改善を始めて、見た目に変化が現れるまでには、少なくとも1ヶ月から3ヶ月はかかると考えて、焦らずじっくりと取り組むことが大切です。
- セルフケアだけで二重顎は解消できますか?
-
解消できる可能性は十分にあります。特に、軽度から中等度の脂肪やたるみ、むくみが原因であれば、
この記事で紹介したようなマッサージ、エクササイズ、生活習慣の見直しを継続することで、かなりの改善が期待できます。
重要なのは、自分の顎下の肉の原因を正しく理解し、それに合ったケアを根気強く続けることです。
ただし、骨格が原因である場合や、脂肪が非常に多い場合など、セルフケアだけでは限界があるケースも存在します。
- 体重は変わらないのに顎下の肉だけ目立つのはなぜですか?
-
主に加齢によるたるみや、姿勢の悪さが原因と考えられます。
年齢とともに肌のハリを支えるコラーゲンが減少し、表情筋が衰えることで、体重に変化がなくても皮膚や脂肪が下がり、顎下がたるんで見えます。
また、長時間のスマートフォン使用などで猫背やストレートネックの姿勢が続くと、血行不良やリンパの滞りが起こり、顎下に老廃物や水分が溜まりやすくなるため、肉が目立つようになります。
体重管理だけでなく、姿勢の改善や表情筋トレーニングが有効です。
- 顎下の肉を落とすのに効果的な食べ物はありますか?
-
特定の食べ物だけで顎下の肉が落ちるということはありませんが、ケアをサポートする食べ物はあります。
むくみ対策には、余分な塩分を排出するカリウムが豊富なバナナ、ほうれん草、海藻類がおすすめです。
また、肌のたるみ対策としては、コラーゲンの材料となるタンパク質(肉、魚、大豆製品)や、その生成を助けるビタミンC(パプリカ、ブロッコリー、キウイフルーツ)を積極的に摂ると良いでしょう。
バランスの取れた食事を心がけることが、すっきりとしたフェイスラインへの近道です。
参考文献
ALLAHYARI FARD, Shahab. Surgical and non-surgical methods in facial rejuvenation. 2018.
ARORA, Gulhima; SHIROLIKAR, Manasi. Tackling submental fat–A review of management strategies. Cosmoderma, 2023, 3.
SALSI, Benedetta; FUSCO, Irene. Non‐invasive system delivering microwaves energy for unwanted fat reduction and submental skin tightening: clinical evidence. Journal of Cosmetic Dermatology, 2022, 21.11: 5657-5664.
HAMMAD, Gamal, et al. Assessment of Double Chin with Exercises and Mesotherapy. Benha Journal of Applied Sciences, 2023, 8.12: 31-37.
THOMAS, Mohan; DSILVA, James. Newer Approaches in Non-surgical Facial Rejuvenation. In: Integrated Procedures in Facial Cosmetic Surgery. Cham: Springer International Publishing, 2021. p. 451-467.
HURST, Eva A.; DIETERT, Jessica Bearden. Nonsurgical treatment of submental fullness. Advances in Cosmetic Surgery, 2018, 1.1: 1-15.
BELTRÁN REDONDO, Beatriz. Non-surgical Abdominal Treatments. In: Post-maternity Body Changes: Obstetric Fundamentals and Surgical Reshaping. Cham: Springer International Publishing, 2023. p. 375-394.
LI, Kelun, et al. Application of nonsurgical modalities in improving facial aging. International journal of dentistry, 2022, 2022.1: 8332631.
SINGLA, Isha; KUMAR, Sanjeev; ARYA, Varun. Facial And Aesthetic Medicine For Oral and Maxillofacial Surgeons. Book Rivers, 2023.